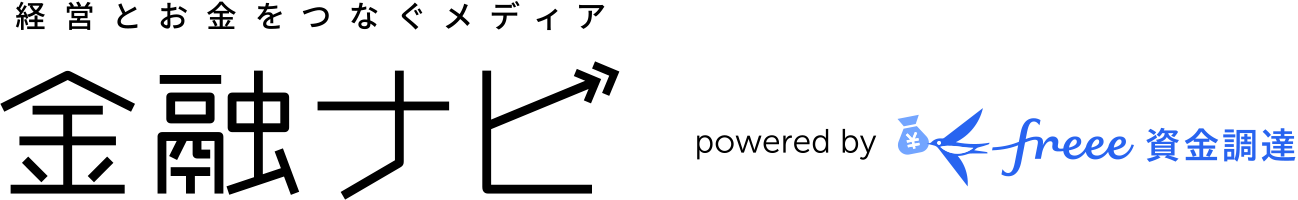うどん屋を開業する流れとポイント|資格や届出、資金調達方法を紹介

うどん屋は個人経営の形態での開業がしやすく安定的なニーズがあることから、起業を考える人に人気ジャンルの一つです。しかし、チェーン店などの競合が多い中で成功させるには、開業前の準備と資金繰りが重要です。本記事ではうどん屋を開業する流れとポイント、必要な資格や届け出、資金調達方法について紹介します。ぜひ参考にしてください。
目次
- うどん屋を開業する流れと押さえておくべきポイント
- うどん屋の開業に必要な資格と届出
- うどん屋の開業資金はどれくらい?
- うどん屋を開業するときの資金調達方法
- 「freee資金調達」で最適な資金調達方法を見つけよう

うどん屋を開業する流れと押さえておくべきポイント

うどんを開業するには、計画的に準備を進めていくことが大切です。まずは、うどん屋を開業する流れと押さえておくべきポイントを紹介します。
コンセプトを決める
他店との差別化を図り、お客様を集客するためにはコンセプトをしっかり検討することが重要です。たとえば、低単価でファミリー向けのお店、素材にこだわった高級志向のお店、セルフサービス型のお店など、多様なコンセプトのうどん屋があります。
自分がどのようなうどん屋を開業したいのか、どのようなうどんを提供したいのかなどを考えながら、コンセプトを明確にしていきましょう。準備に必要なものやアピールポイントが明確になることで、開業準備をスムーズに進めやすくなります。
出店する物件を探す
うどん屋を経営していく上で、物件や立地は非常に重要なポイントです。ただし、好立地の物件は物件取得費や家賃が高い傾向にあり、物件にコストをかけすぎると経営を圧迫してしまう原因になることもあるため慎重に検討する必要があります。
物件を探す際はコンセプトとコストのバランスを意識することが大切です。出店する地域の事前調査が行い、適切な物件を探すようにしましょう。また、理想的な物件を探すには時間がかかることが多いため、早い段階で物件を探し始めることをおすすめします。
仕入先を見つける
うどんはシンプルなメニュー構成であるゆえに、他店と差別化するためには素材にこだわるなどの工夫が必要があります。とくに麺やつゆはお店の味を決定づける重要な要素です。コンセプトやコストを意識しつつ、自社が求める素材を提供してくれる仕入先を選ぶようにしましょう。
集客対策を講じる
街にはうどん屋だけでなく、様々な飲食店が出店しています。自店を選んでもらえるように、積極的に集客施策を実施していきましょう。具体的には、以下のものがあります。
- ホームページの作成
- Googleマイビジネスの登録
- メディアや雑誌への掲載
- リスティング広告
- SNSの開設・発信
- ポスティングや新聞折込み
- 貼り紙・ポスター
GoogleマイビジネスではGoogle Mapに店舗情報を登録できます。最近は地図アプリ上の店舗情報やクチコミを参考にするユーザーが多く、Googleマイビジネスは集客に有効な施策となっています。Googleアカウントを登録するだけなので、簡単に始められます。
SNSも基本的に無料で始めることができるため、おすすめの施策です。写真や動画が拡散されれば、より多くの集客が期待できます。
その他にもコストをかけることで、様々な集客施策を実施することが可能です。効果的な集客施策は地域やターゲットによって異なるため、分析しながら最適な集客施策を見つけていきましょう。
うどん屋の開業に必要な資格と届出

うどん屋を開業するためには、開業前に取得すべき資格や届出があります。スムーズに開業準備を進めるためにも、必要な資格や届出を把握しておきましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者はその名の通り、飲食店の衛生を管理する責任者です。飲食店を運営する経営者は、1店舗につき1名以上の食品衛生責任者を配置しなければいけません。食品衛生責任者は、以下のいずれかの要件を満たすことで取得することができます。
- 調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格を保有している
- 食品衛生責任者講習会を受講する
食品衛生責任者講習会は各都道府県の食品衛生協会が定期的に実施しています。受講料は1万円程です。なお、食品衛生責任者はお店に常駐する人が取得する決まりとなっています。2つ以上の店舗を運営する場合は、その店舗ごとの食品衛生責任者が必要です。
飲食店営業許可
飲食店を営業するためには、飲食店営業許可が必要です。許可証を受けずに営業してしまうと食品衛生法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。飲食店営業許可を取得するには、以下が要件となっています。
- 1店舗に1人以上の食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の施設検査
- 営業許可書の取得
飲食店営業許可は保健所に店舗の図面を提出し、施設検査に通ることで交付されます。許可の条件は管轄の保健所によって若干異なるため、事前相談にて詳しい説明を聞いておきましょう。
防火管理責任者
防火管理責任者は店舗の収容人数(スタッフを含む)が30人を超える飲食店が取得しなければいけない資格です。延床面積に応じて「甲種」と「乙種」に分類されます。
- 甲種:延床面積が300㎡以上
- 乙種:延床面積が300㎡未満
防火管理責任者を取得するためには、各地域の消防署が実施している防火・防災管理講習を受けることで必要です。甲種では2日間、乙種では1日の講習期間を要します。延べ面積や必要書類を確認した上で、最寄りの消防署へ連絡しましょう。
開業届
うどん屋を開業する際は、事務所を管轄している税務署に開業届を提出します。開業届を提出することで、確定申告において青色申告を選択することが可能です。青色申告の場合、最大65万円の特別控除を受けることができるなど、税制上のメリットを享受できます。
うどん屋の開業資金はどれくらい?

うどん屋の開業資金は、規模によって大きく変わります。費用の内訳を以下にまとめました。ただし、金額はあくまで目安なので、開業時にはしっかり数値を計算して計画的に進めていきましょう。
|
費用 |
金額 |
|---|---|
|
物件取得費 |
500万円〜1,000万円 |
|
内装・外装工事費 |
400万円〜600万円 |
|
厨房設備費 |
100万円〜500万円 |
|
備品購入費 |
30万円〜50万円 |
|
広告宣伝費 |
20万円〜 |
うどん屋に限らず、飲食店の経営が安定するまでには半年以上かかるといわれています。お店が軌道に乗るまでの期間を加味して、運転資金は最低でも3ヶ月から6ヶ月を目安に用意しておくことを推奨します。
うどん屋を開業するときの資金調達方法

ここでは、うどん屋を開業するときの資金調達方法を紹介します。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は政府が100%出資している金融機関です。民間の銀行では実績がない経営者への融資は渋られるケースが多くなりますが、日本政策金融公庫は創業期の小規模事業者・個人事業主を積極的に支援しています。
なかでも「新創業融資制度」は、無担保・無保証人かつ低金利で借り入れすることができることから、多くの事業者が利用しています。
なお、新創業融資制度では「創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること」という要件を設けています。必要総額の3割程度を目安に、一定以上の自己資金が貯まってから融資を検討することをおすすめします。
補助金・助成金
補助金・助成金は国や地方自治体が提供している補助制度です。税金や雇用保険料が主な財源となっており、返済の必要はありません。
補助金・助成金は種類が多く、応募期間や条件は様々です。関係省庁や地方自治体、商工会議所などにて補助金・助成金の情報が公開されています。新しい補助金・助成金も随時更新されているので、情報を逃さないように常にアンテナをはってキャッチしましょう。
制度融資
制度融資とは、地方自治体・民間金融機関・信用保証協会の3機関が連携して提供している融資制度です。制度融資は金利が低く、長期間の借り入れが可能という特徴があります。自治体によって内容や種類が異なるため、事業所所在地の制度融資の内容・条件をしっかり確認する必要があります。
また、制度融資は金融機関・地方自治体・信用保証協会の3機関が関与するため、審査に時間を要するのが一般的です。開業スケジュールに支障がないかを確認しながら申し込むようにしましょう。
「freee資金調達」で最適な資金調達方法を見つけよう

うどん屋を開業するには、計画性のある準備と資金繰りが重要です。とくに資金繰りに関しては、「適切な資金調達方法がわからない」と悩む方もいるのではないでしょうか。
そんな経営者の悩みを解決する手段として「freee資金調達」をご紹介します。「freee資金調達」は、Web上に条件を入力するだけで様々な資金調達手段から自社に最適なものを見つけられるサービスです。
freee資金調達の大きな特徴は以下の通りです。
・入力条件をもとに、各金融機関で実際に融資を受けられる可能性があるか予測
※「可能性診断」機能つき
・即日利用開始可能で、急な資金繰りにも対応
※登録時間はわずか10分
・一度入力した情報が保存されるので、また資金が必要になった時に、すぐに調達手段を確認できる
freee資金調達は無料で利用できます。「資金を調達したいけれど、自店に適した調達手段がわからない」という方は、ぜひfreee資金調達を活用して開業時や運営にお役立てください。
- ローン商品や給付金等の情報は、特に断りがない限り記事公開現在のものです。最新の情報は各金融機関のホームページや公式サイトでご確認ください。
- freee資金調達はお客様のサービス選択時の参考情報提供を目的としており、特定の金融機関、ローン商品の優劣を示したものではありません。
- 各金融機関の審査結果によっては利用できない場合があります。