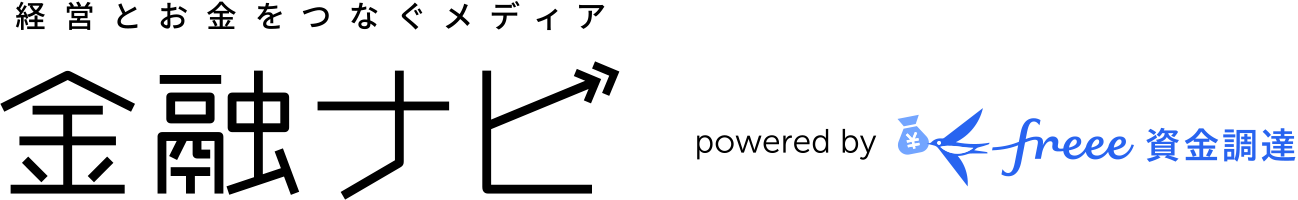新規事業に活用できる助成金の種類|メリットや補助金との違いも解説

「新規事業を始めたいが資金が足りない」「事業を始めたが資金繰りに苦戦している」など、新規事業の立ち上げ時は資金面での悩みが多く挙げられます。資金調達にはさまざまな方法がありますが、できるだけ少ないリスクで資金調達することが望ましいといえます。
国や地方自治体が提供している「助成金」は返済不要のお金であり、新規事業者が優先的に検討したい制度です。当記事では、助成金を活用するメリットと新規事業で活用できる助成金を4つピックアップして紹介します。
目次

新規事業に助成金を活用するメリット

新規事業において助成金を活用するメリットは、次のように整理できます。
返済が不要
助成金の大きなメリットは、返済が不要であるということです。通常は自己資金に加え、さまざま方法で必要な資金を調達する必要があります。
日本政策金融公庫や民間の金融機関からの融資は代表的な資金調達方法ですが、当然ながら期日までの返済義務があり、利子も支払う必要があります。そのため、しっかりとした返済計画を組まないと、資金繰りに窮するリスクがあります。
一方で、助成金には返済義務がありません。これは、助成金の財源が雇用保険料の一部から賄われているためです。労働者を雇って事業を行えば雇用保険料を払うことになるので、助成金を受け取る権利があるということです。
労働環境の見直し・改善につながる
助成金を申請するには、就業規則・雇用契約書・賃金台帳などの提出が求められます。書類を準備する際に不備や漏れがないか目を通すことになるため、結果的に労働環境の把握や労働関連法の遵守、適正な労働管理につなげることができます。
また助成金は、従業員の教育訓練や処遇改善などの取り組みを補助するものが多く、活用することで労働環境の向上につながります。従業員が働きやすい環境・制度をつくることができ、自社のイメージアップや取り組みのアピールにも効果が期待できます。
実績になる
助成金を受給できるということは、「職場環境が整っている」「事業計画が明確である」など国から自社の事業が認められたという実績になります。企業の信頼度が増し、今後の融資などにおいても有利に働きます。
助成金と補助金の違いとは

助成金と補助金はどちらも国が提供している返済不要のお金であり、事業者を支援する制度です。
助成金と補助金の大きな違いは、審査の有無です。助成金は応募要件を満たせば、原則受け取ることができます。
対して補助金は、採択件数や予算があらかじめ決まっているため、審査を通過しないと受給されません。審査を通過するためには、事業計画と資金使途を具体的にした事業計画を作成し、事業の妥当性や必要性をアピールする必要があります。
新規事業で利用できる助成金

ここでは新規事業で使える助成金を4つ紹介します。
- キャリアアップ助成金
- 人材開発支援助成金
- 地域中小企業応援ファンド
- 創業助成事業(東京都)
助成金は事業者を支援する制度であり、社会の情勢や事業者のニーズに合わせて新しいものが公募されています。
また、助成金には地方自治体が独自で行っているものもあります。該当する地域の助成金についても常にチェックするようにしましょう。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規労働者(有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者)のキャリアアップ促進を目的とした助成金です。非正規労働者の正社員化や処遇改善などの取り組みを実施した事業者に対して、助成金が支給される仕組みです。
令和4年4月1日から制度の一部が変更されます。変更点について下記で解説していきます。
①助成対象の一部廃止(正社員コース)
これまでのキャリアアップ助成金では、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換も助成対象で、一人あたり28万5,000円を支給していました。改正後は、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成は廃止となります。
〈変更後の助成対象〉
- 有期雇用労働者から正規労働者への転換:1人あたり57万円
- 無期雇用労働者から正規労働者への転換:1人あたり28万5,000円
②正規労働者・非正規労働者の定義の変更(正社員化コース、障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金の対象となる正規労働者の条件が追加され、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規労働者に変更されます。
また、非正規労働者の定義にも条件が追加されます。改正前は6ヶ月以上雇用している有期または無期雇用労働者でした。改正後は、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けている有期または無期雇用労働者に変更されます。
※なお、これら定義の変更は令和4年10月1日以降の正社員転換に適用されます。
③加算の廃止(賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース)
これらのコースでは、対象労働者が増えるごとに助成金が支給される加算制度が適用されていました。改正後は、2人目以降にかかる加算が廃止されます。
④支給要件の変更(賞与・退職金制度導入コース)
これまでの賞与・退職金制度導入コースでは、諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化が支給要件となっていました。改正後は、賞与または退職金の制度新設に変更されます。
⑤支給要件の緩和および時限措置の延長(短時間労働者労働時間延長コース)
短時間労働者労働時間延長コースは、有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成されるものです。改正後は、週所定労働時間の要件が週5時間以上から週3時間以上に緩和されます。
また、助成額の増額措置等が延長され、令和4年9月末から令和6年9月末(予定)に変更されます。
ただし、これらの内容は今後も変更となる可能性があります。常に新しい情報をキャッチするようにしましょう。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、事業主が労働者に対して訓練(職務に関連した専門的な知識や技能の習得)を実施した場合、その際にかかった訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を補助する制度です。
事業を成長させるためには人材育成が重要です。人材開発支援助成金は、従業員の資質向上やモチベーションアップにつながる資格取得に対して助成金を受け取ることができるため、計画的に人材育成を行うことができます。
令和4年度からは、内容の一部見直しが検討されています。コースごとに内容や要件が変わる予定となっています。
地域中小企業応援ファンド
地域中小企業応援ファンドは、中小機構や各都道府県の役所、地方の金融機関などが共同で出資している地域独立型ファンドです。
地域中小企業応援ファンドには「地域中小企業応援ファンド」と「農商工連携型中小企業
応援ファンド」の2種類があり、都道府県の状況に応じて組成されています。中小企業や農林漁業者が行う、商品開発や販路開拓の取り組みにかかる費用を支給します。
詳しい対象や内容は各都道府県によって異なります。下記の中小機構のホームページにて詳細を確認することができるので、参考にしてください。
→地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)|中小機構
創業助成事業(東京都)
創業助成金は、都内開業率の向上を目的に東京都が独自に支給している助成金です。東京都で創業後5年以内の事業者を対象に、導入費や広告費、創業にかかる費用の一部を補助しています。助成率は3分の2以内、限度額は300万円です。
公募期間が決まっているので、都内で創業する予定の事業者は最新の情報をチェックしてみてください。
「freee資金調達」で最適な資金調達方法を見つけよう

助成金は、年々新しい制度が登場しているほか、地方自治体が独自に行っているものもあります。自社に活用できる助成金がないか、常に最新の情報に目を配り申請期間に遅れないようにしましょう。
経営者の悩みを解決する手段として「freee資金調達」をご紹介します。
「freee資金調達」は、Web上に条件を入力するだけで、さまざまな資金調達手段から自社に最適なものを見つけられるサービスです。freee資金調達の大きな特徴は以下の通りです。
・入力条件をもとに各金融機関で実際に融資を受けられる可能性があるかを予測
※「可能性診断」機能つき
・即日利用開始可能で、急な資金繰りにも対応
※登録時間はわずか10分
・一度入力した情報が保存されるので、また資金が必要になった時にすぐに調達手段を確認できる
freee資金調達は無料で利用できます。「資金を調達したいけれど、自店に適した調達手段がわからない」という方は、ぜひfreee資金調達を活用し、事業の経営にお役立てください。
- ローン商品や給付金等の情報は、特に断りがない限り記事公開現在のものです。最新の情報は各金融機関のホームページや公式サイトでご確認ください。
- freee資金調達はお客様のサービス選択時の参考情報提供を目的としており、特定の金融機関、ローン商品の優劣を示したものではありません。
- 各金融機関の審査結果によっては利用できない場合があります。